脊髄損傷とは
ここでは脊髄損傷とはどういうものなのか、その概要や症状、合併症について解説していきます。
概要

脊髄損傷とは、何らかの要因で脊髄が損傷した状態です。脊髄は末端で感じた感覚を脳に伝える、もしくは脳からの指令を伝える役割があります。歩くことや座ること、冷たいものに冷たいと感じる、暑い部屋に行って暑いと感じるのはいずれも脳からの指令や末端で感じたことなどが関係しています。脊髄損傷の状態だと感覚が機能しなくなる麻痺状態になるのです。
基本的には外からの圧力・衝撃で損傷してしまい、交通事故や高所からの転落、転倒などが該当します。またスポーツを行っている際に脊髄損傷になるケースも多く、競馬の騎手が落馬によって脊髄損傷になるケースもあります。
脊髄損傷は年間5,000人ほどが受傷するとされ、年代に応じて受傷原因は異なります。若い人は交通事故や転落、スポーツ、年齢を重ねる中で平地転倒の割合が増えていく傾向にあるのも特徴です。
症状
脊髄損傷の症状は損傷した部位や損傷具合によって大きく異なります。ここからは症状について詳しく解説します。
発症部位

発症部位に関してはそれぞれの部位で区分けされており、頸椎はC1からC7、胸椎はT1~T12、腰椎はL1からL5、仙椎はS1からS5に分けられています。
分かりやすく説明すると、発症部位から下の部分が働きにくい状態となります。例えば胸椎で損傷が起きれば、頸椎は損傷していないため上半身は動かせるものの、下半身は動かしにくく、感覚も消えてしまうのです。
そのため、発症部位が上にいけばいくほど、症状は深刻なものとなり、生命の維持で精一杯という事態を招きます。
例えば、頭を守る頸椎の場合、C1~3の部位で損傷が起きると横隔膜などが動かせなくなるため、自力での呼吸ができません。そのため、人工呼吸器を使わないと生命の維持ができなくなってしまうのです。一方同じ頸椎でもC6~8の部位での損傷だと横隔膜は動かせるため、呼吸自体はできますが、腹式呼吸しかできないなど、発症部位の違いでかなりの違いがみられます。
知覚麻痺
知覚麻痺は脊髄が損傷することで感覚情報が脳に伝わらない状態を指します。脊髄は脳から指令を伝え、末端から情報を受け取るための伝達路ですが、損傷によって末端からの伝達路が遮断されてしまい、手足などの感覚がわからないなどの状態になったのが知覚麻痺です。
皮膚などにある受容器で熱い、冷たい、痛いなどの情報をつかみ、その情報を脊髄に向かって信号を送り、脊髄から脳に向かって伝達されることで、熱いや痛いなどの情報を把握できます。知覚麻痺だと、熱いや痛いなどの情報が入りようがない状態にあります。
完全麻痺
完全麻痺は完全損傷とも呼ばれ、損傷した部位における運動機能が完全になくなり、感覚自体も失われた状態を指します。
伝達路が損傷した部位を境に完全に分断される形となるため、完全麻痺になってしまうと、部位全体の機能が停止されたような状態になり、コントロールがきかない状態になってしまいます。
不全麻痺
不全麻痺は不全損傷とも呼ばれ、運動機能の一部が失われた状態です。一部が失われた状態なので、完全になくなったわけではなく、一部の機能のコントロールは可能です。
運動機能や感覚など一部分は機能しているため、リハビリによって麻痺している部分をカバーすることで日常生活を送ることもできます。
一方で脊髄損傷直後は「脊髄ショック」と呼ばれる状態に陥り、完全麻痺と不全麻痺の見分けがつかなくなることがあります。事故などで脊椎損傷などのケガを負った場合にはこれ以上損傷部分を大きくしないよう、できる限り固定してから病院に搬送され治療を受け、完全麻痺か不全麻痺かを見極めることになるでしょう。
合併症
脊髄損傷には完全麻痺や不全麻痺の他にも合併症が存在します。ここでは合併症のケースを解説します。
尿路障害・腸管障害
脊髄損傷により、尿管や腸管が麻痺してしまい、尿路障害や腸管障害を起こします。いずれの障害も最初はうまく排泄できない状態となり、膀胱に尿がたまる一方だったり、下痢を引き起こしてから便秘になったりする状態です。
尿路障害の場合は薬で対処できるケースがある一方、集尿器やカテーテルを活用しないと対応できないケースもあります。腸管障害は今までの排便だと対応できないため、食事の対応や浣腸の活用、排便スタイルの工夫など様々な形で対応しなければなりません。
自律神経機能障害
自律神経機能障害は自律神経関連の障害を指します。脊髄損傷は自律神経にも影響を与えてしまうのです。症状としては血圧が急に上下するなど様々な影響をもたらしてしまいます。こうした現象を「自律神経過反射」と呼び、先ほどの尿路障害などが自律神経を強く刺激してしまうことで起こりやすくなります。
体温調節機能に障害をもたらすほか、脈が速い頻脈の状態、末梢血管拡張症、起立性調節障害など自律神経に関連する各種症状が出てしまうため、注意が必要です。
関連記事
人気の記事
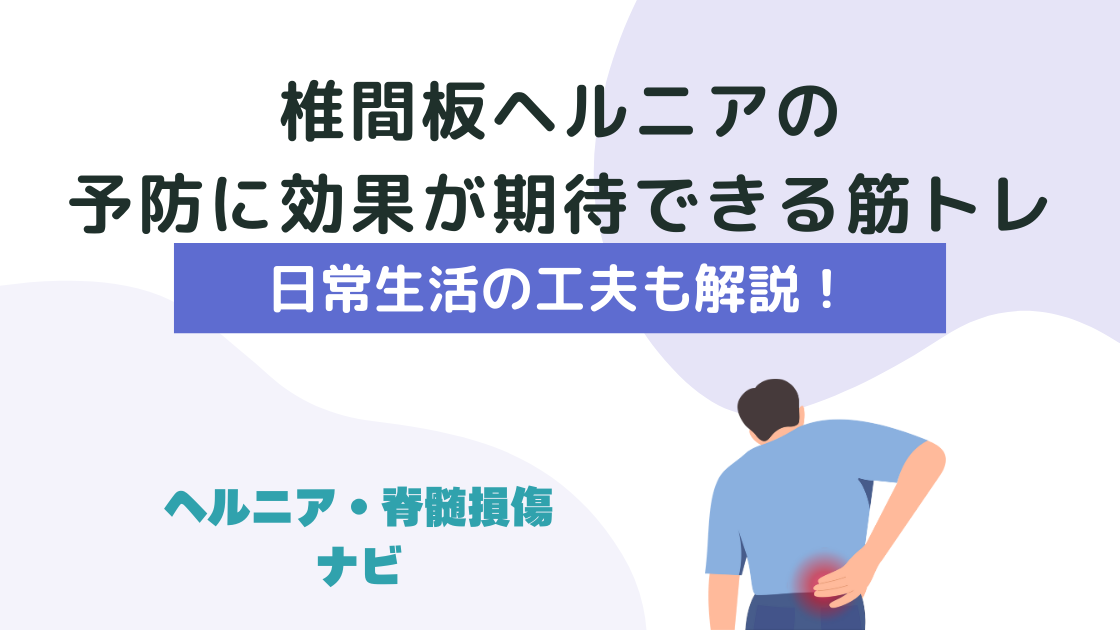
椎間板ヘルニアの予防に効果が期待できる筋トレと日常生活の工夫
つらい腰痛や下半身のしびれは、椎間板ヘルニアの可能性があります。椎間板ヘルニアは、年齢や生活習慣を問わず、誰もが発症する可能性のある疾患です。近年、デスクワークの増加や運動不足により、発症リスクが高まっていると言われています。 この記事では…
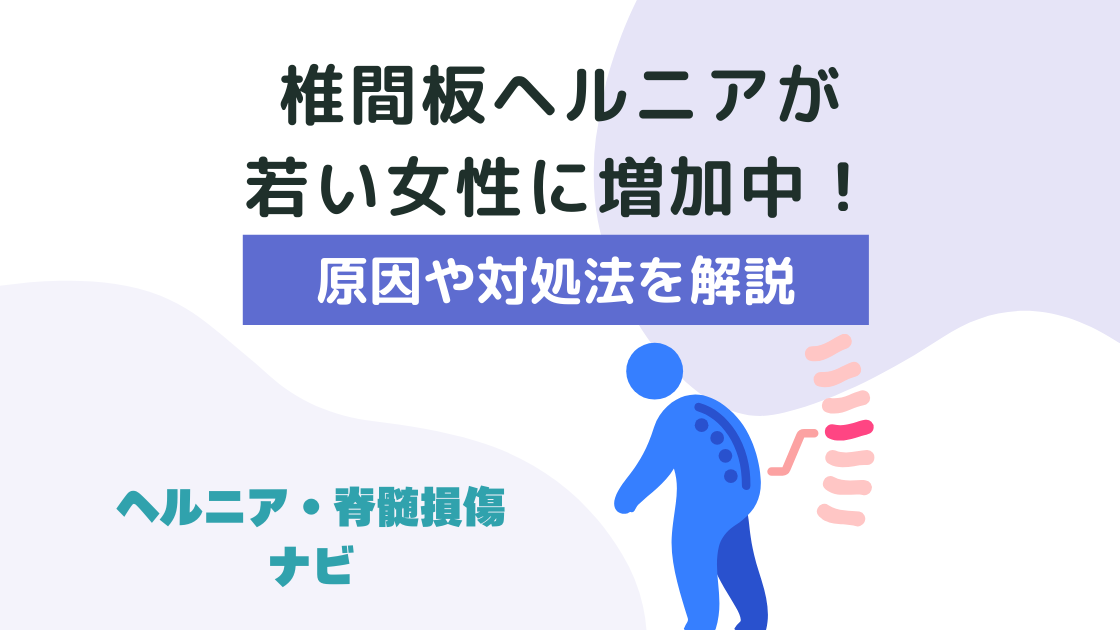
椎間板ヘルニアが若い女性に増加中!原因と効果が期待できる対処法
最近、腰や脚に違和感を覚えていませんか?若い女性の間で椎間板ヘルニアが増えています。椎間板ヘルニアは、背骨のクッション材である椎間板が変形・突出することで神経を圧迫し、激しい痛みやしびれを引き起こす疾患です。放っておくと日常生活にも支障をき…
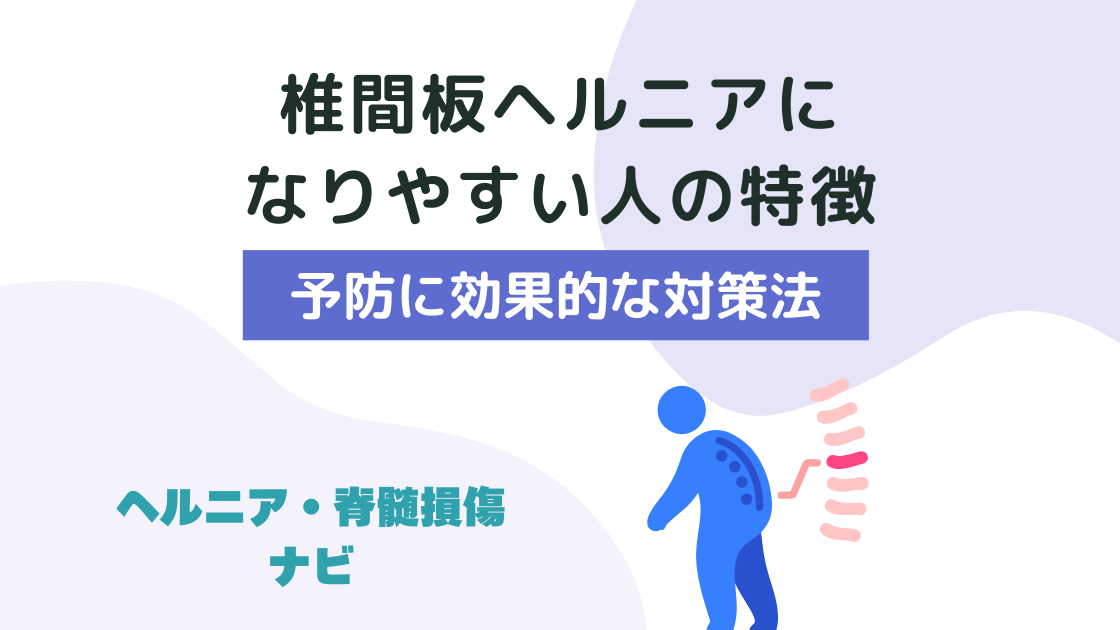
椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴と予防に効果的な対策法
腰や首に違和感や痛みがある場合は、椎間板ヘルニアの初期症状である可能性があります。椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板(クッションの役割)が飛び出して、神経を圧迫することで、腰や首に痛みやしびれを引き起こす病気です。 デスクワーク中心の生…
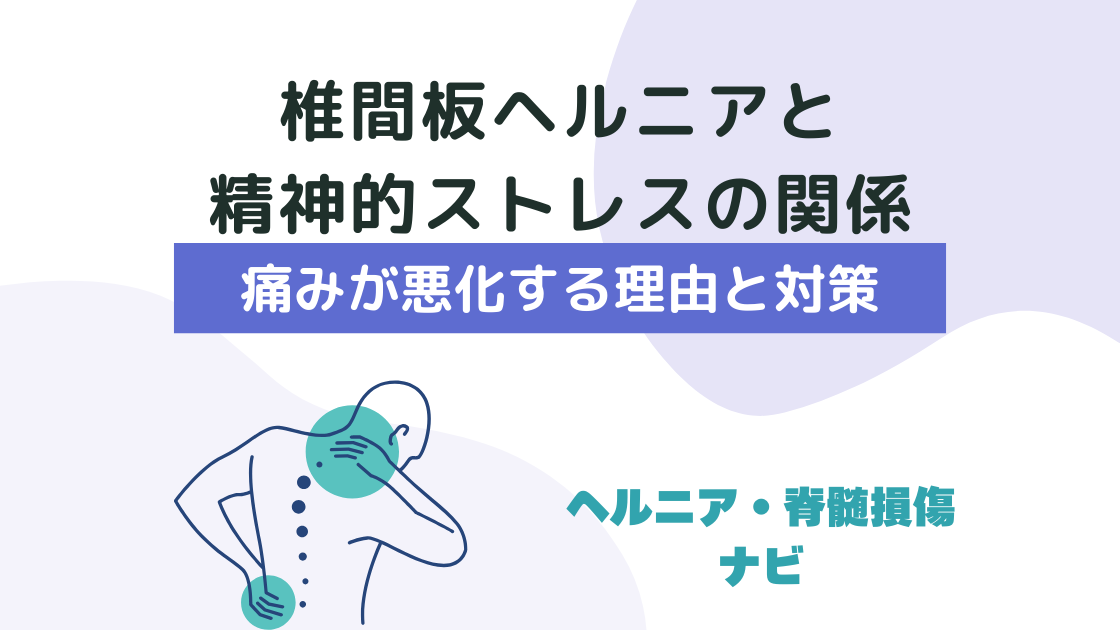
椎間板ヘルニアと精神的ストレスの関係|痛みが悪化する理由と対策を紹介
朝起きたときや気分が落ち込んだときに腰の痛みが悪化する場合は、椎間板ヘルニアと精神的ストレスの関連性を疑ってみてください。ストレスは筋肉の緊張や血行不良を招き、椎間板ヘルニアの痛みを増幅させる原因です。ストレスの影響で痛みが慢性化してしまう…

頚椎椎間板ヘルニアの症状とその影響!効果的な改善法
頚椎椎間板ヘルニアは、首の痛みや手のしびれ、動かしにくさなどの症状が現れることがあります。特に30代以降の成人に見られる、比較的一般的な疾患です。この記事では、頚椎椎間板ヘルニアの症状や、効果的な改善策、日常生活で気をつける点を解説します。…
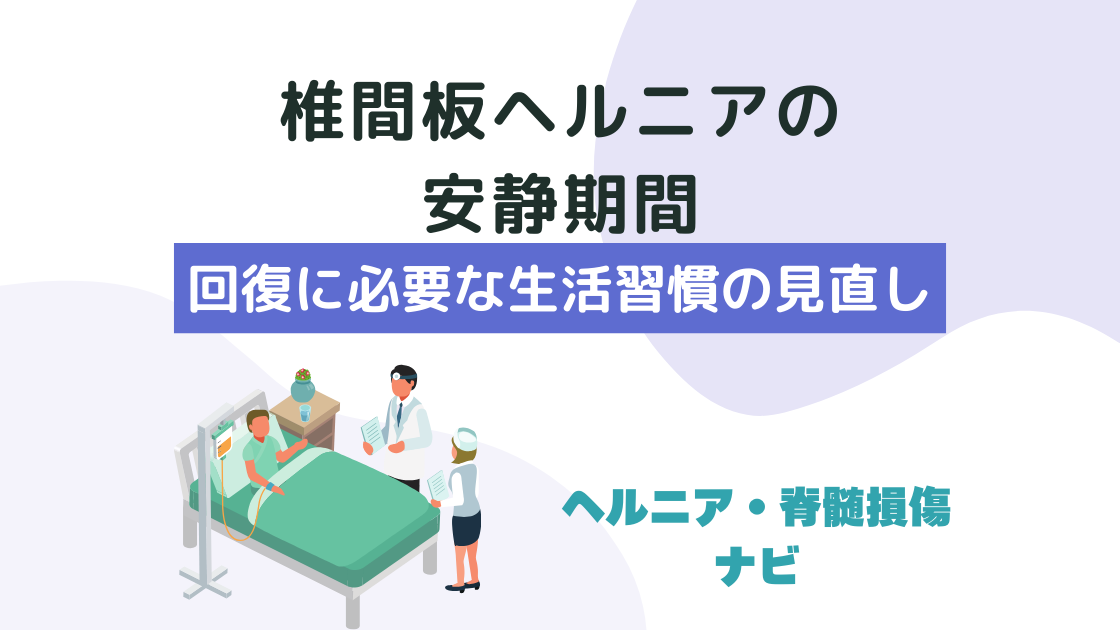
椎間板ヘルニアの安静期間と回復に必要な生活習慣の見直し
腰や足の痛みや、しびれがある場合「もしかして椎間板ヘルニアかも?」と不安を抱える方は少なくありません。椎間板ヘルニアは、背骨のクッションである椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす疾患です。安静期間の目安や、動いても…
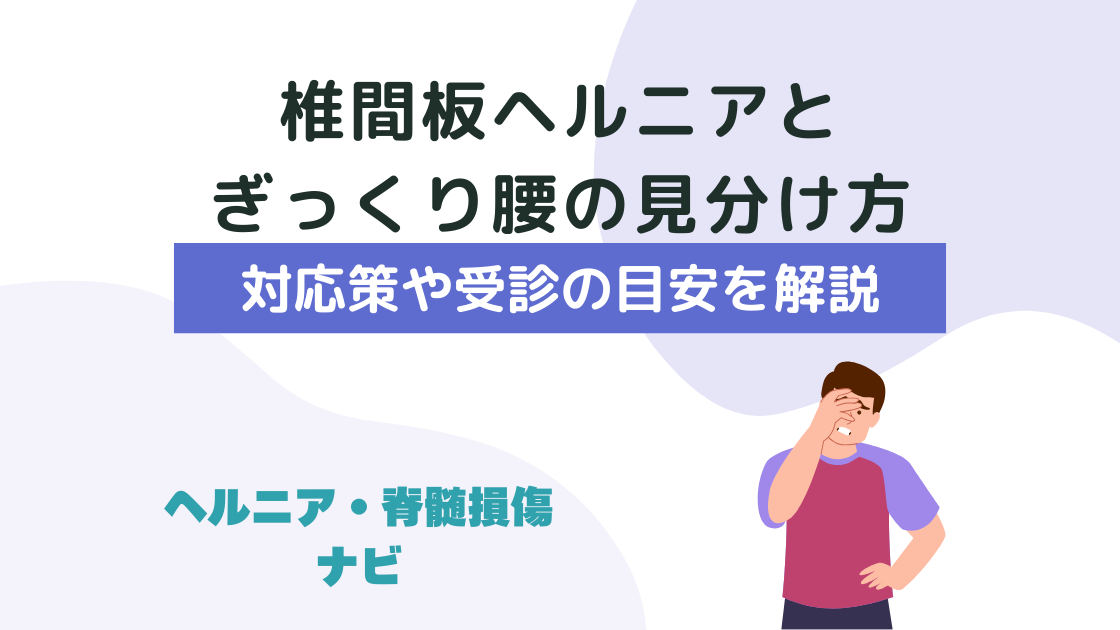
椎間板ヘルニアとぎっくり腰の見分け方|対応策や受診の目安を解説
腰に痛みを感じたとき「椎間板ヘルニア?」「ぎっくり腰?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。どちらも腰痛を伴うため自己判断は難しく、医療機関の受診が大切です。この記事では、椎間板ヘルニアとぎっくり腰の違いを4つのポイントでわかりやすく…
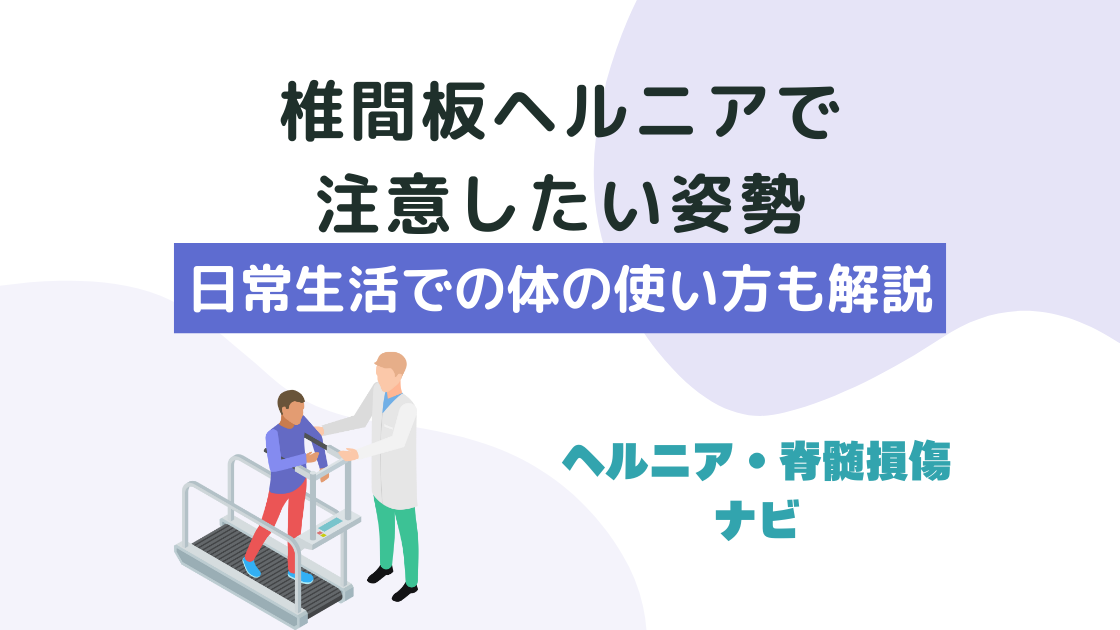
椎間板ヘルニアで注意したい姿勢と日常生活での体の使い方を解説
腰や脚の痛みやしびれに悩まされていませんか?実は、腰や脚の痛みなどの症状は間違った姿勢が原因である可能性があります。現代人の多くが患う椎間板ヘルニアは、日常生活の姿勢と密接に関係しており、間違った姿勢を続けているとヘルニアが悪化してしまう場…
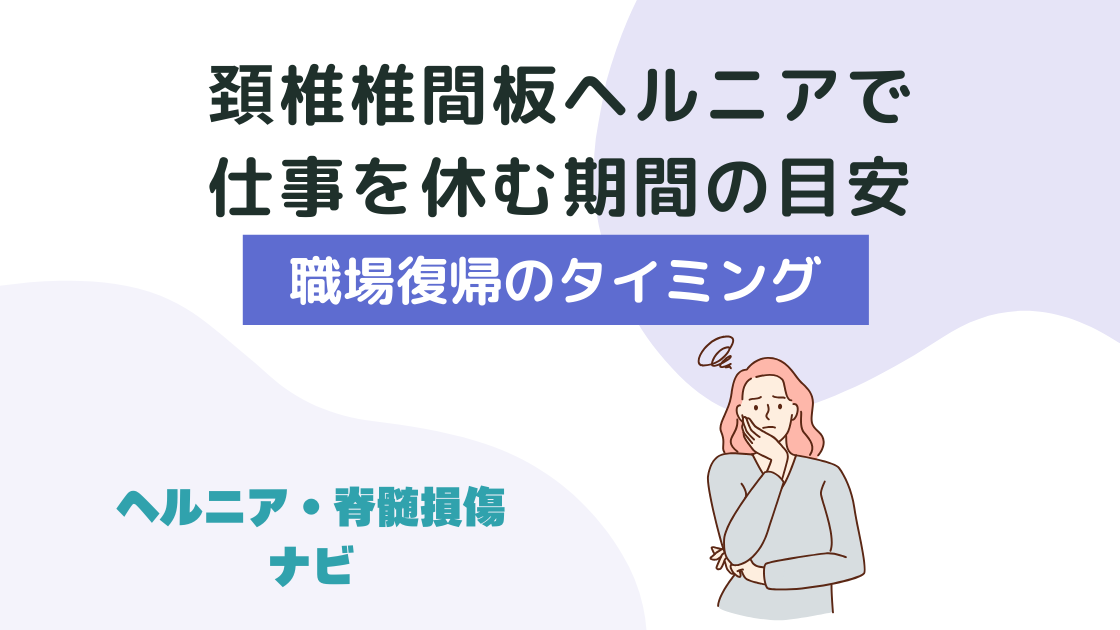
頚椎椎間板ヘルニアで仕事を休む期間の目安と職場復帰のタイミング
首や肩の痛み、腕や手のしびれが続く場合、頚椎椎間板ヘルニアの可能性があります。悪化すると日常生活だけでなく、仕事にも大きな支障をきたすおそれがあります。症状によっては通勤や業務の継続が困難となり、休職が必要になることもあります。特に長時間の…
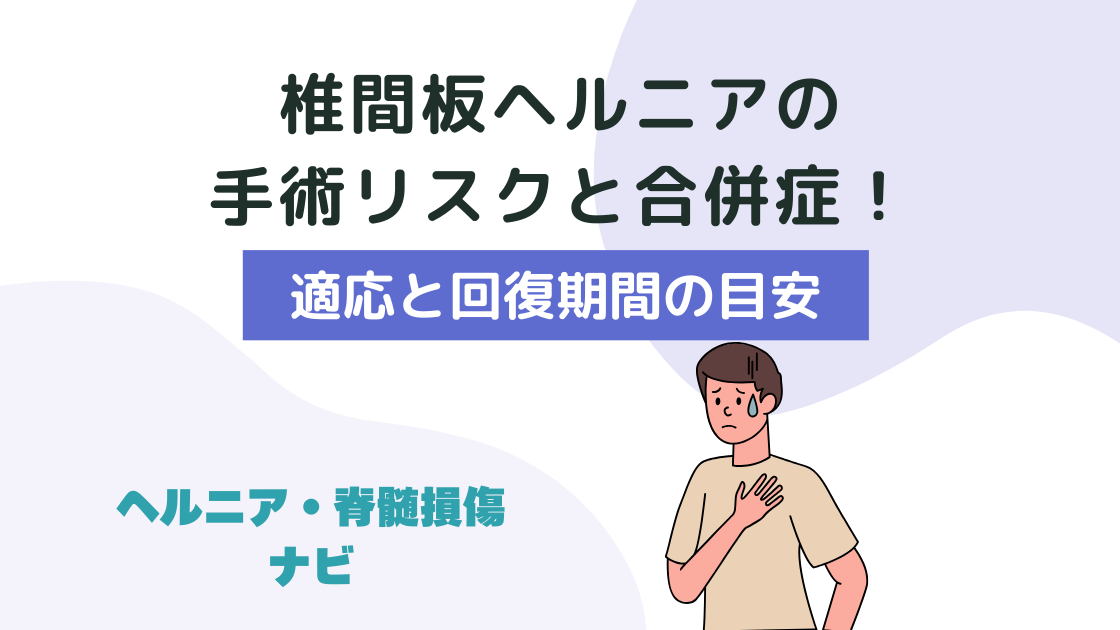
椎間板ヘルニアの手術リスクと合併症!適応と回復期間の目安
腰に痛みやしびれを感じている方は、椎間板ヘルニアの可能性があります。椎間板ヘルニアの診断を受けると、手術への不安を感じる方が多くいます。手術は症状の改善に効果が期待できる治療法ですが、感染症や神経損傷、合併症が生じる可能性があります。 この…
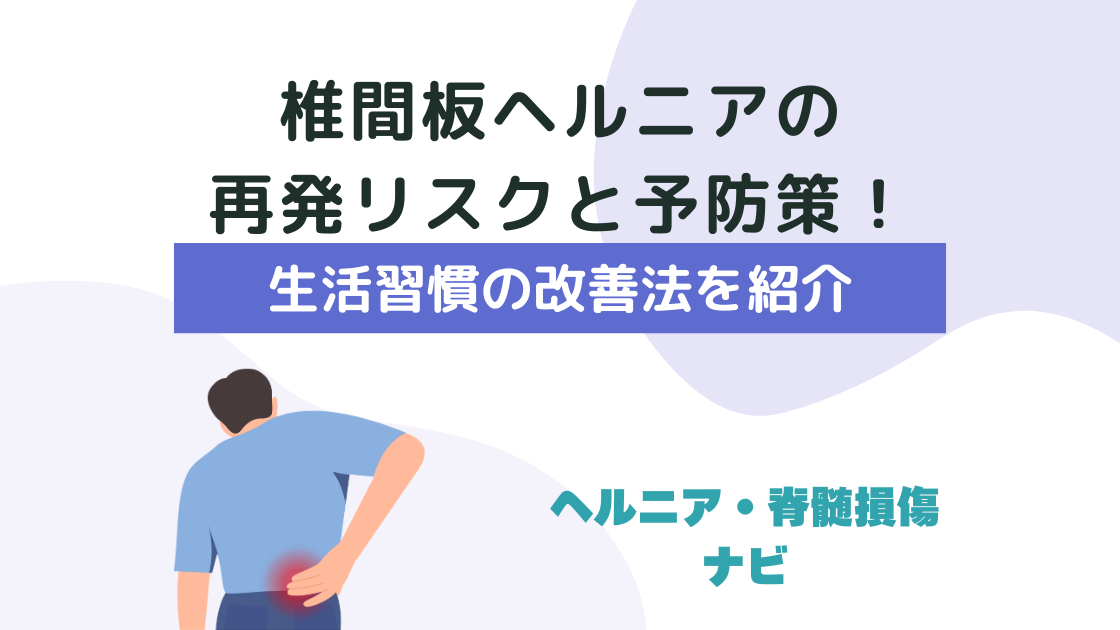
椎間板ヘルニアの再発リスクと予防策!生活習慣の改善法を紹介
椎間板ヘルニアを経験した方は、再発の不安があるのではないでしょうか。日常の何気ない行動や生活習慣が、再発リスクを高める場合があります。本記事では、手術後のリハビリテーションの重要性や、日常生活で気をつけるべき点、コルセットの効果的な使用方法…

膝が痛いのは椎間板ヘルニアが原因かも|見逃しやすい症状と受診の目安
膝の痛みの原因が、実は膝ではなく腰の椎間板ヘルニアにあることは珍しくありません。椎間板の異常によって神経が圧迫されると、腰の痛みだけでなく、膝にもしびれや痛みが現れることがあります。 本記事では、椎間板ヘルニアと膝の症状との関連性や特徴、受…
戻る
