脊髄損傷の予防法
予防するには
脊髄損傷を予防するには、医療で行える予防法、普段の生活で行える予防法の2つのパターンがあります。
医療でできる予防法
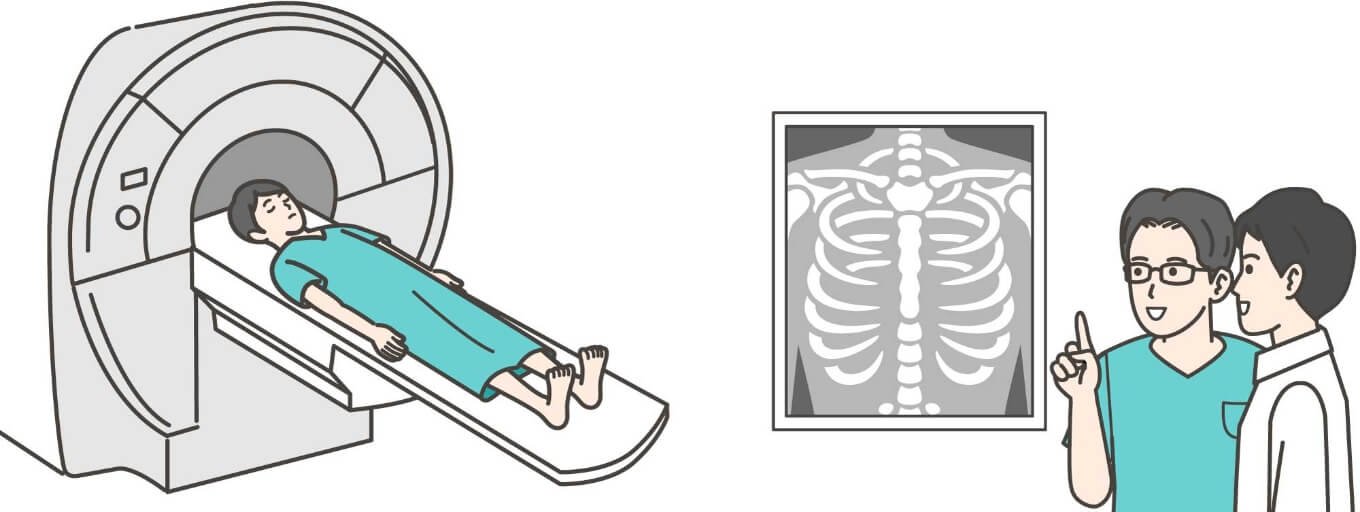
医療で行える予防法の1つには人間ドックを行うことが挙げられます。特におすすめなのが脊椎ドックと呼ばれるものです。
脊椎ドックとは脊椎周辺の画像検査などを行う中で病気がないかをチェックするものです。本来は数週間程検査がかかる中で、脊椎ドックであればたった1日で終わります。脊椎ドックは頸椎・胸椎・腰椎とそれぞれ行えるほか、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の有無、大動脈瘤の状態など、のちの危険因子のチェックが行えます。
脊椎ドックを行う病院は数えるほどしかないのがネックですが、病院によっては宿泊施設を割安で利用できる形になっており、遠方から足を運んで脊椎ドックを受けるケースもあるほどです。
こうした検査では脊椎や脊髄に腫瘍が見つかることもあります。仮に腫瘍が見つかれば、無症状だと定期的なMRI撮影で経過観察を行い、症状があれば手術を行います。脊椎腫瘍には転位性脊椎腫瘍と呼ばれる、他の部位でのがんが脊椎に転移したケースもあり、この場合は放射線治療などを行うことになります。
脊髄腫瘍や脊髄出血、脊髄梗塞などは早期発見や早期治療を行うことで悪影響を最小限にとどめることが可能です。
普段の生活での予防法
普段の生活でも脊髄損傷を予防していくことは可能です。ここからは普段の生活で私たちが気を付けたいことをまとめていきます。
作業前・スポーツ前の安全確認
外傷性脊髄損傷は2018年だけで6000人以上の方が発症し、その発生率は100万人あたりで49人という結果が日本脊髄障害医学会が行った外傷性脊髄損傷に関する全国調査で明らかになっています。
この調査において、交通事故が原因のケースが目立ちますが、交通事故を予防することはシートベルトの着用や安全運転に心がける程度で、巻き込まれるケースもあることから自力で予防するのには限度があります。
しかし、高所からの転落や落下物による下敷き、もしくはスポーツ時の受傷などは事前に安全確認を徹底することでおおよそ防ぐことは可能です。安全対策が十分ではない場合には安全対策を施すほか、安全対策を要求し、叶わない場合には取りやめるということも必要となります。
高所からの転落も安全が確認されていない場所で作業をする中で発生することがあるため、安全対策が万全かどうかを確認するだけでも脊髄損傷のリスク低減につながるでしょう。
転倒防止
年齢を重ねていく中で急激に増えていくのが転倒です。特に平地での転倒が大きく、階段での転倒よりも多い傾向にあります。不慮の事故によって亡くなる方は、元々テクノロジーの進化や安全対策が進んだこともあって減少傾向にある中、高齢者が平地で転倒して亡くなるケースは年々増えています。
モチを詰まらせるなどして窒息して亡くなる方が高齢者における不慮の事故の代表例でしたが、現状は転倒や転落などで亡くなるケースが追い抜いた状態です。つまり、高齢者における転倒や転落への対策は進んでいるとは言えない状況となります。
平地での転倒の要因では年齢を重ねていることはもちろん、元々の持病、薬の影響、運動不足などが重なっていることが背景にあります。できる限り転倒しないよう、安全対策を施すことだけでなく、部屋の整理をする、そして、日ごろから運動を行うことが大切です。
生活習慣病対策
脊髄梗塞、脊髄出血など血管で起きた症状から結果的に脊髄損傷を誘発するケースがあります。脊髄梗塞の場合には大動脈解離などが原因で起こりますが、この大動脈解離は動脈硬化や高血圧、糖尿病、喫煙などが要因で起こりやすく、特に高血圧は危険とされています。
脊髄に血流が流れにくくなって脊髄損傷につながるパターンでも動脈硬化の影響が大きいことが挙げられており、生活習慣病になることが脊髄損傷を誘発する可能性を高めると言えるでしょう。
日ごろから生活習慣病対策を行うことで、脊髄損傷を誘発する諸症状を避けることができます。食事管理や運動などをしっかりと行っていき、生活習慣病を避けることで脊髄梗塞や脊髄出血のリスクを下げていきましょう。
応急処置も予防法の1つ
交通事故や作業時の事故などで外傷性脊髄損傷になってしまうことがありますが、これらの事故に直面した際にいきなり外傷性脊髄損傷を疑ってかかる人は多くありません。しかし、受傷して間もない場面における応急処置により、脊髄損傷の悪化を防ぎ、後遺症などを最小限にとどめていくことは可能です。
1秒でも早く救急隊を要請することは当然ですが、時間がかかりそうな場合には両手を使って頭部などを固定してケガを負った人物に話しかけて頭を動かさないように求めていくことが必要です。
結局、身体を動かすなどして脊髄損傷を悪化させる可能性があるため、できる限り動かさないことが求められます。そして、専門的な知識を持つ救急隊に委ねるべき作業でもあります。ただ、様々な事情もあって救急隊がなかなか来そうにないなどの事態において、緊急的に行いましょう。
関連記事
人気の記事
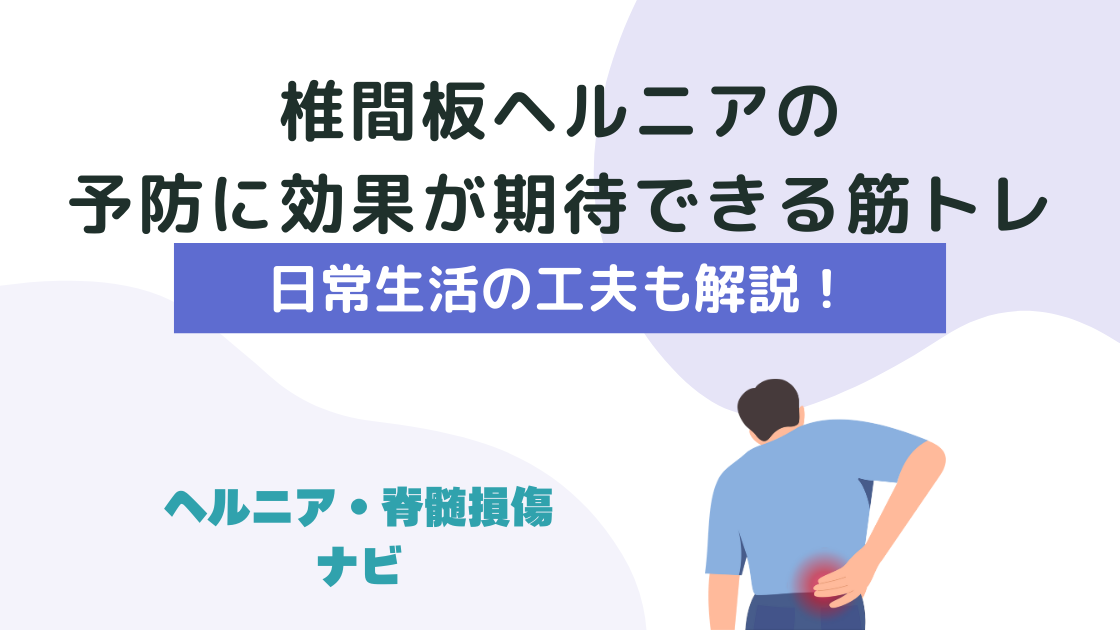
椎間板ヘルニアの予防に効果が期待できる筋トレと日常生活の工夫
つらい腰痛や下半身のしびれは、椎間板ヘルニアの可能性があります。椎間板ヘルニアは、年齢や生活習慣を問わず、誰もが発症する可能性のある疾患です。近年、デスクワークの増加や運動不足により、発症リスクが高まっていると言われています。 この記事では…
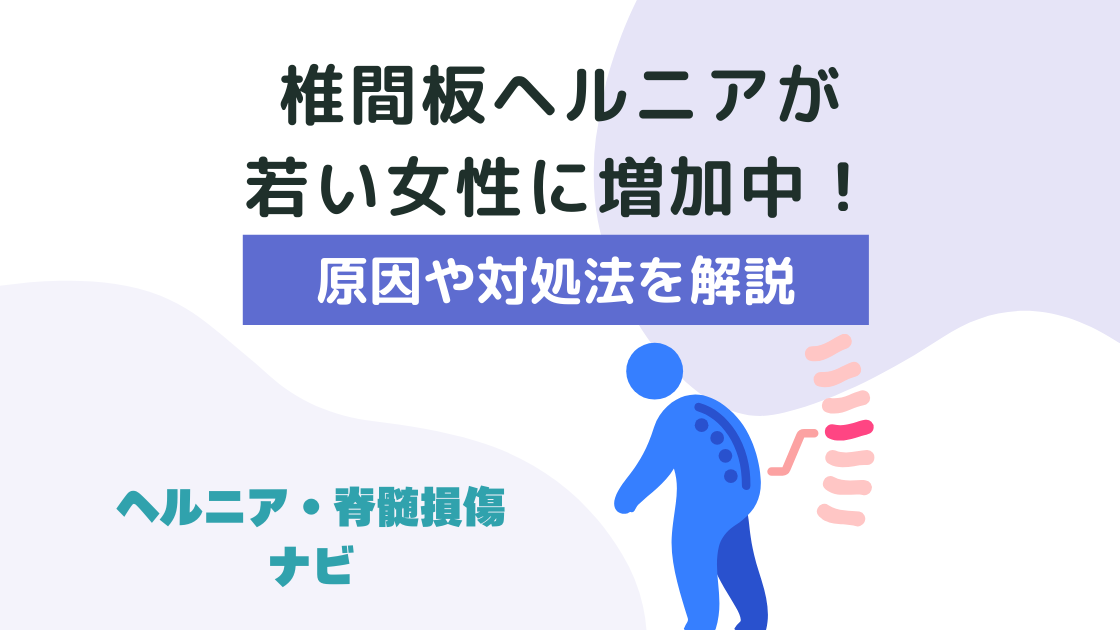
椎間板ヘルニアが若い女性に増加中!原因と効果が期待できる対処法
最近、腰や脚に違和感を覚えていませんか?若い女性の間で椎間板ヘルニアが増えています。椎間板ヘルニアは、背骨のクッション材である椎間板が変形・突出することで神経を圧迫し、激しい痛みやしびれを引き起こす疾患です。放っておくと日常生活にも支障をき…
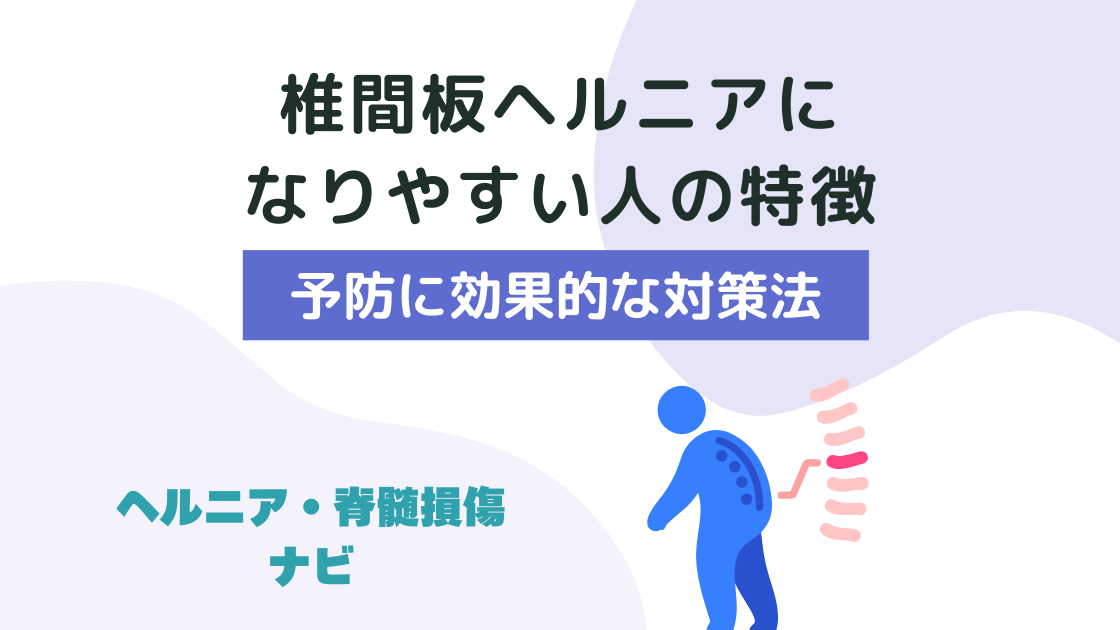
椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴と予防に効果的な対策法
腰や首に違和感や痛みがある場合は、椎間板ヘルニアの初期症状である可能性があります。椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板(クッションの役割)が飛び出して、神経を圧迫することで、腰や首に痛みやしびれを引き起こす病気です。 デスクワーク中心の生…
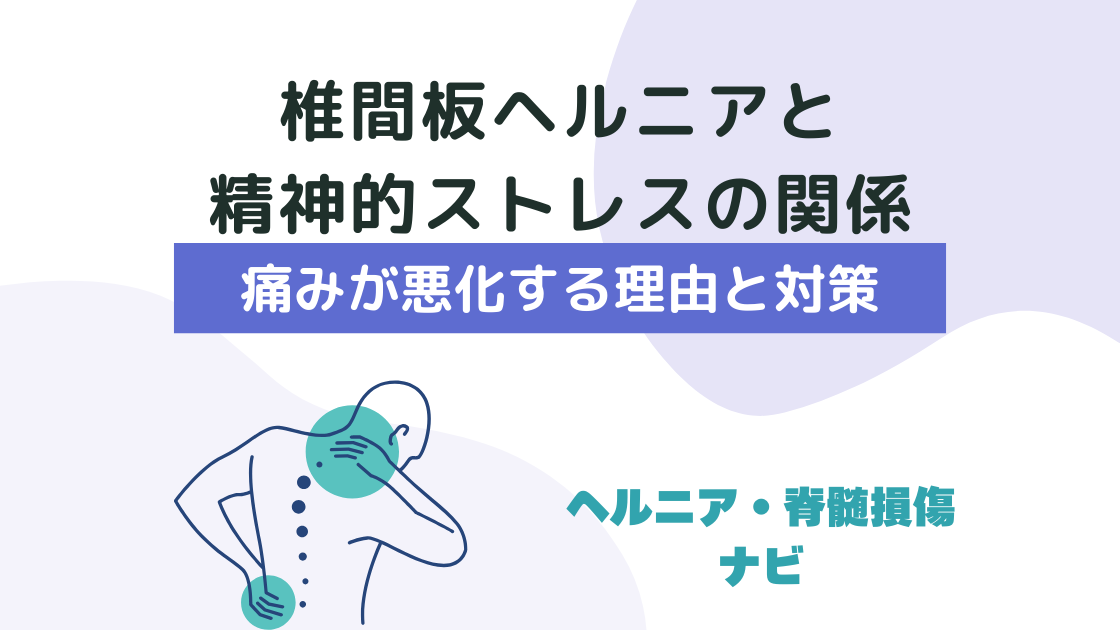
椎間板ヘルニアと精神的ストレスの関係|痛みが悪化する理由と対策を紹介
朝起きたときや気分が落ち込んだときに腰の痛みが悪化する場合は、椎間板ヘルニアと精神的ストレスの関連性を疑ってみてください。ストレスは筋肉の緊張や血行不良を招き、椎間板ヘルニアの痛みを増幅させる原因です。ストレスの影響で痛みが慢性化してしまう…

頚椎椎間板ヘルニアの症状とその影響!効果的な改善法
頚椎椎間板ヘルニアは、首の痛みや手のしびれ、動かしにくさなどの症状が現れることがあります。特に30代以降の成人に見られる、比較的一般的な疾患です。この記事では、頚椎椎間板ヘルニアの症状や、効果的な改善策、日常生活で気をつける点を解説します。…
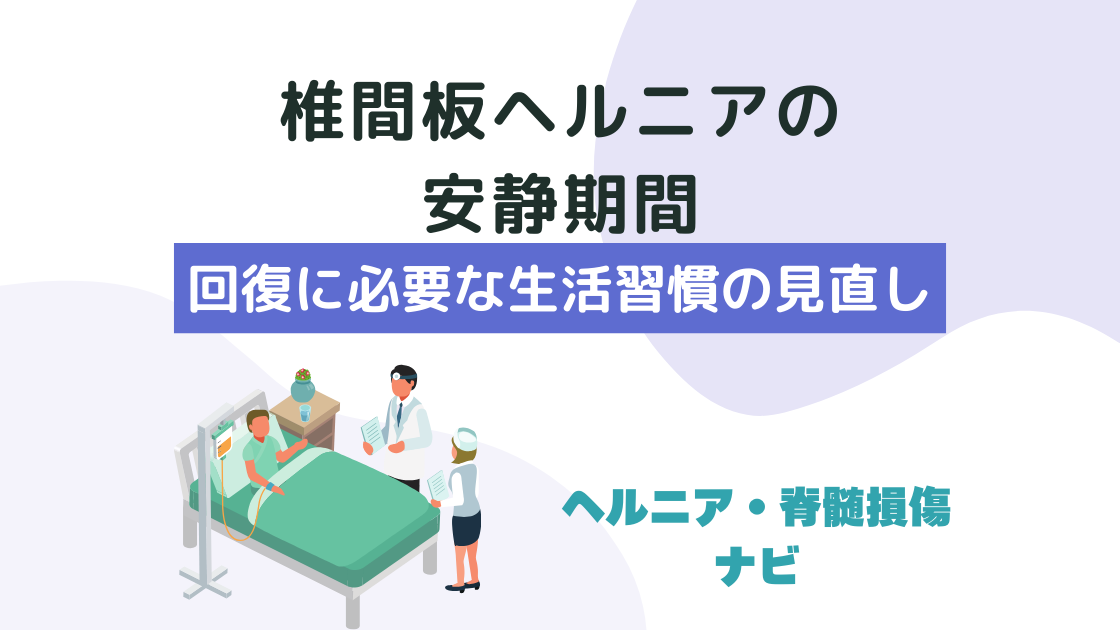
椎間板ヘルニアの安静期間と回復に必要な生活習慣の見直し
腰や足の痛みや、しびれがある場合「もしかして椎間板ヘルニアかも?」と不安を抱える方は少なくありません。椎間板ヘルニアは、背骨のクッションである椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす疾患です。安静期間の目安や、動いても…
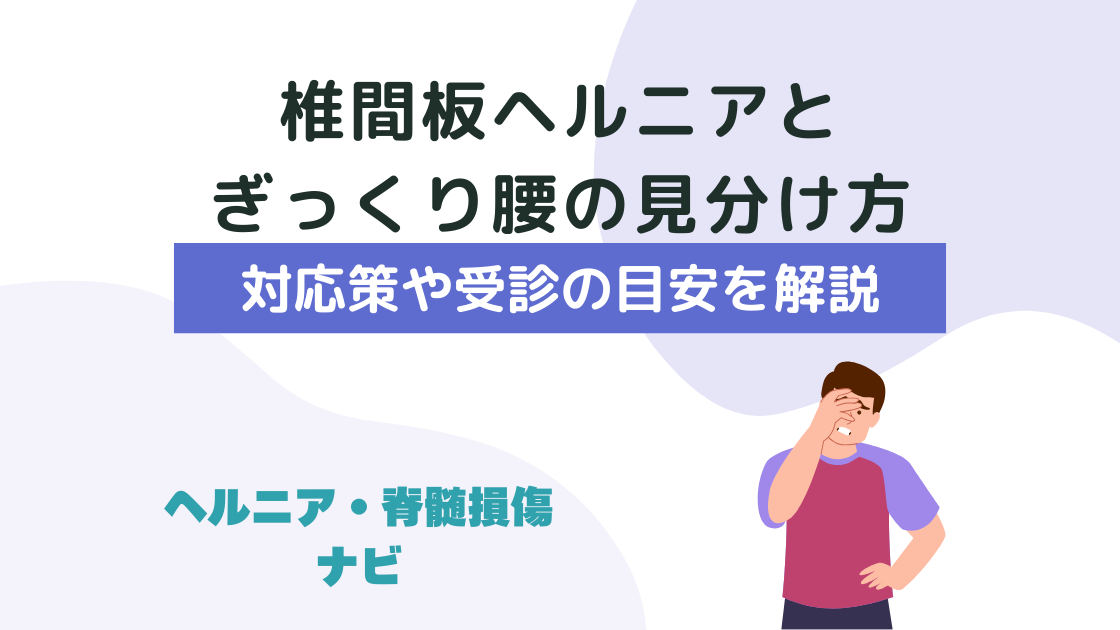
椎間板ヘルニアとぎっくり腰の見分け方|対応策や受診の目安を解説
腰に痛みを感じたとき「椎間板ヘルニア?」「ぎっくり腰?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。どちらも腰痛を伴うため自己判断は難しく、医療機関の受診が大切です。この記事では、椎間板ヘルニアとぎっくり腰の違いを4つのポイントでわかりやすく…
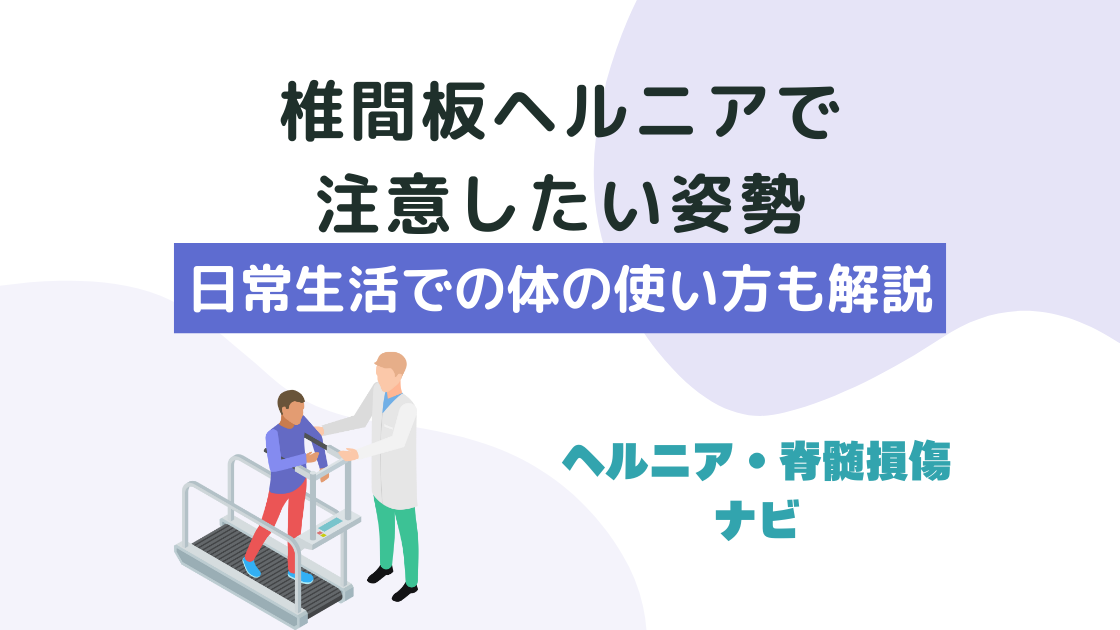
椎間板ヘルニアで注意したい姿勢と日常生活での体の使い方を解説
腰や脚の痛みやしびれに悩まされていませんか?実は、腰や脚の痛みなどの症状は間違った姿勢が原因である可能性があります。現代人の多くが患う椎間板ヘルニアは、日常生活の姿勢と密接に関係しており、間違った姿勢を続けているとヘルニアが悪化してしまう場…
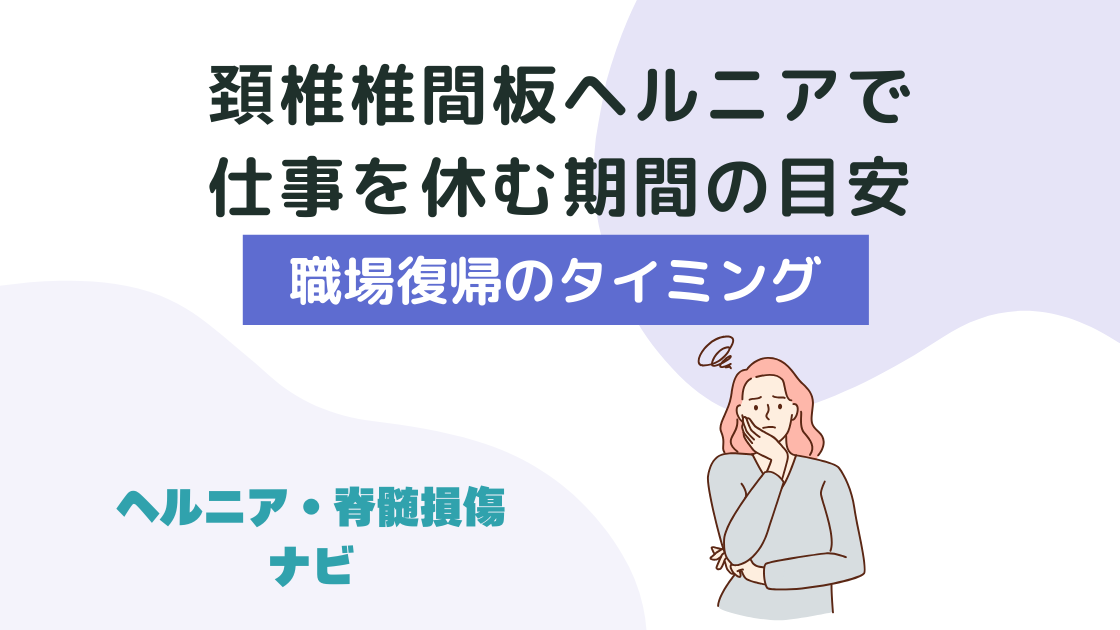
頚椎椎間板ヘルニアで仕事を休む期間の目安と職場復帰のタイミング
首や肩の痛み、腕や手のしびれが続く場合、頚椎椎間板ヘルニアの可能性があります。悪化すると日常生活だけでなく、仕事にも大きな支障をきたすおそれがあります。症状によっては通勤や業務の継続が困難となり、休職が必要になることもあります。特に長時間の…
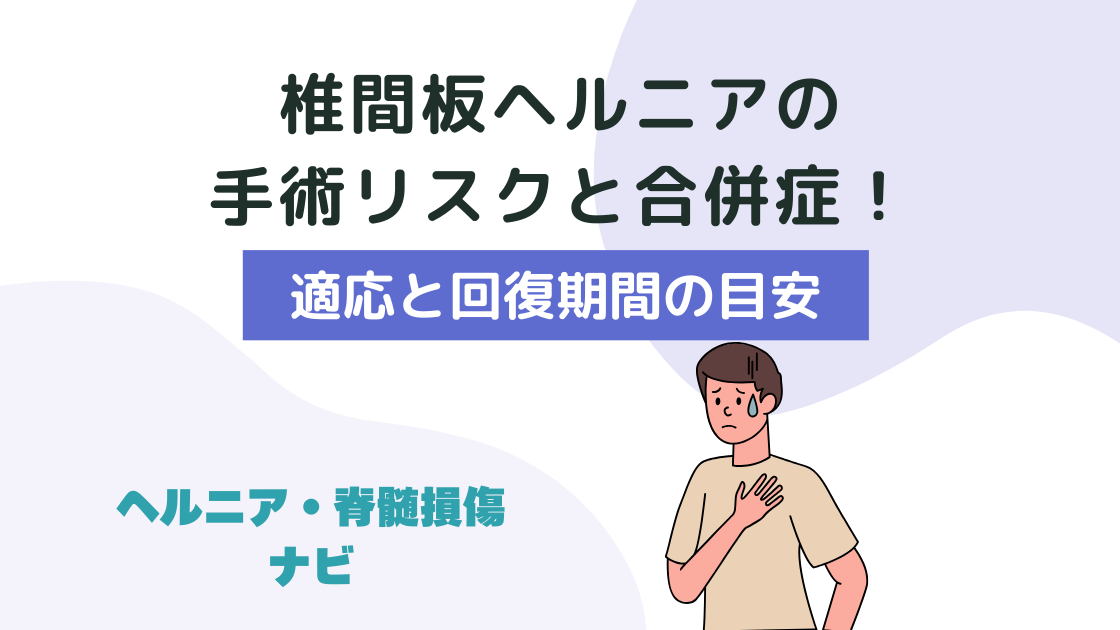
椎間板ヘルニアの手術リスクと合併症!適応と回復期間の目安
腰に痛みやしびれを感じている方は、椎間板ヘルニアの可能性があります。椎間板ヘルニアの診断を受けると、手術への不安を感じる方が多くいます。手術は症状の改善に効果が期待できる治療法ですが、感染症や神経損傷、合併症が生じる可能性があります。 この…
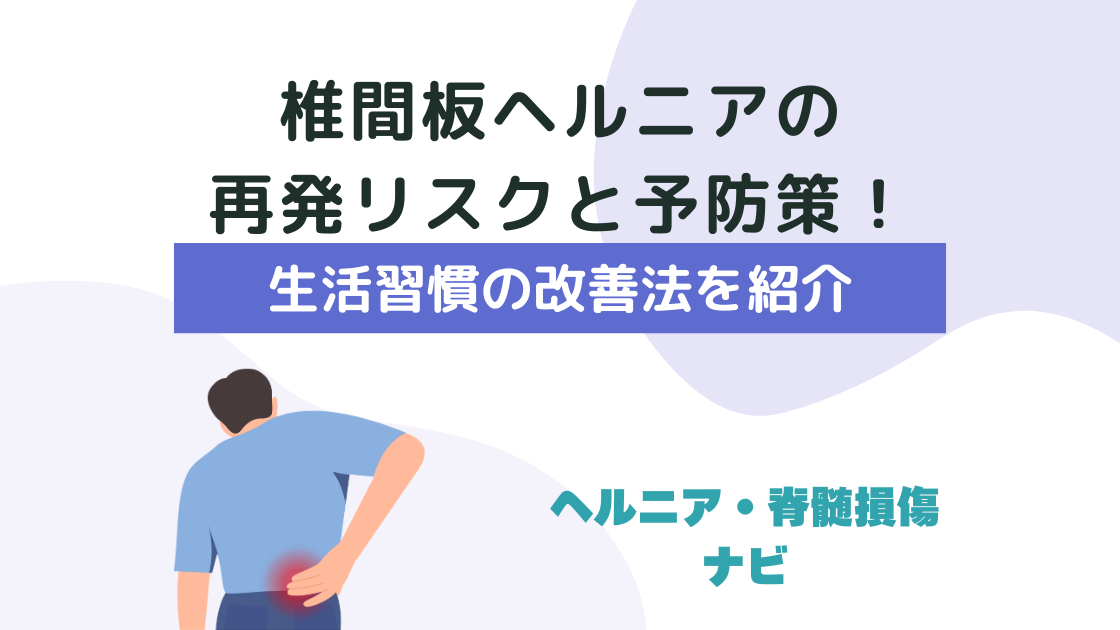
椎間板ヘルニアの再発リスクと予防策!生活習慣の改善法を紹介
椎間板ヘルニアを経験した方は、再発の不安があるのではないでしょうか。日常の何気ない行動や生活習慣が、再発リスクを高める場合があります。本記事では、手術後のリハビリテーションの重要性や、日常生活で気をつけるべき点、コルセットの効果的な使用方法…

膝が痛いのは椎間板ヘルニアが原因かも|見逃しやすい症状と受診の目安
膝の痛みの原因が、実は膝ではなく腰の椎間板ヘルニアにあることは珍しくありません。椎間板の異常によって神経が圧迫されると、腰の痛みだけでなく、膝にもしびれや痛みが現れることがあります。 本記事では、椎間板ヘルニアと膝の症状との関連性や特徴、受…
戻る
